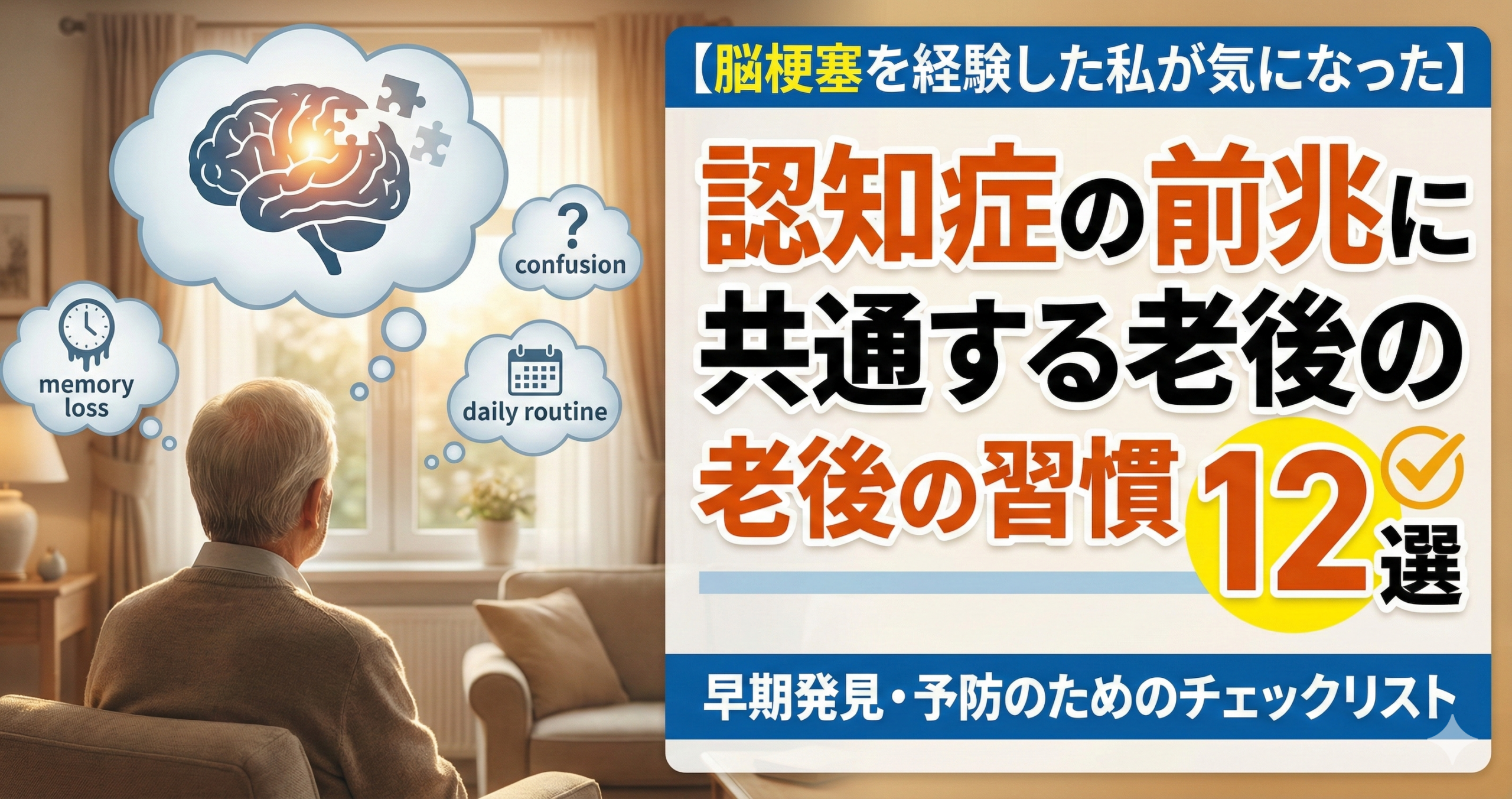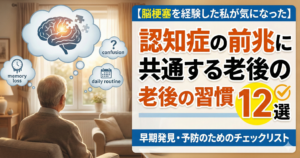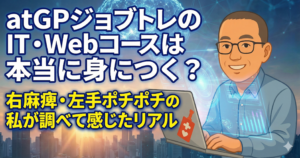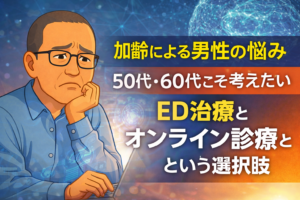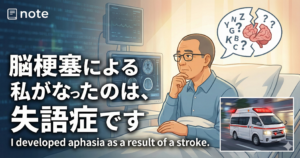【脳梗塞を経験した私が気になった】認知症の前兆に共通する老後の習慣12選
こんにちは、しげです。
私は2022年に脳梗塞を発症し、右半身麻痺と失語症が残りました。右手はほとんど動かず、最初はスマホの操作すら思うようにできませんでした。
還暦を目前にして、
「もう何もできないのかもしれない」
そんなふうに絶望した時期も、正直あります。
それでも今は、左手一本でスマホとパソコンをポチポチしながら、無理のない形でAIを使った副業にも取り組んでいます。
そして最近、強く気になっているのが「認知症」です。
脳梗塞を経験したからこそ、「脳の調子」は他人事ではありません。
ただ、認知症の話は怖くなりがちです。
だから私は、怖さをそのまま抱えるのではなく、続けられる小さな習慣に変えていくことを意識しています。
その代表が 毎日の散歩 です。私はいま、ほぼ毎日 30分〜1時間 歩いています。
体調に合わせて、ゆっくりでも、途中で休んでもいい。それでも「歩く」という積み重ねが、心と頭を支えてくれている感覚があります。
この記事では、医療的な診断をするのではなく、認知症の“前兆っぽさ”につながりやすい 老後の共通習慣を12個に整理し、さらに後半で「今日からの整え方」までまとめます。
※この記事は医療的な診断をするものではありません。気になる症状が続く場合は、かかりつけ医や専門外来へご相談ください。
そもそも認知症とは?(むずかしく言うと“生活に支障が出る脳の変化”)
認知症は、脳の病気などによって、記憶・判断・言葉・段取りなどの認知機能が下がり、日常生活に支障が出てくる状態のことです。
よく「物忘れ=認知症」と思われがちですが、ポイントはここです。
“物忘れ”と“認知症っぽさ”の違い(目安)
- 物忘れ:体験の一部を忘れる(例:朝ごはん何食べたっけ?)
- 認知症っぽさ:体験そのものが抜けたり、生活の管理が崩れやすい(例:食べたこと自体を覚えていない、支払いを何度も忘れる)
もちろん境目は簡単ではありません。
だからこそ「早めに気づいて整える」価値があります。
認知症の前兆につながりやすい「老後の習慣」12選
ここからが本題です。
認知症は原因がひとつではありませんが、リスクを上げやすい生活パターンには共通点があります。
(※“やっている=認知症”ではありません。増えてきた/続いている、が目安です)
1. 人と話す機会が減る(社会的孤立が進む)
老後に一番増えやすいのが「人と話さない日」が続くことです。
会話が減ると、言葉を探す・相手に合わせる・思い出す、といった脳の働きを使う機会も減ってしまいます。
最初は「面倒だから今日はいいか」でも、それが続くと外出も減り、気づかないうちに孤立が習慣化します。
対策は大きくなくて大丈夫です。
週1回の電話、散歩中の会釈、LINEスタンプ1つでも“つながり”は残せます。脳を守るのは、実はこういう小さな接点だったりします。
2. 家の中で座りっぱなしが増える(活動量が落ちる)
座っている時間が増えると、体力だけでなく気力も落ちやすくなります。すると「出かけるのがしんどい」→「さらに動かない」の流れができてしまう。
老後は仕事や用事が減るぶん、意識しないと“動く理由”がなくなります。
対策は「運動しよう」ではなく、生活の中に混ぜることです。
買い物は遠回りする、階段を少し使う、家の中を数分歩く。完璧は要りません。
まずは“ゼロ”をなくすだけで、体と脳の流れが変わりやすくなります。
3. 散歩習慣がない(外の刺激が減る)※ここに固定
私はいま、ほぼ毎日 30分〜1時間 歩いています。
脳梗塞のあと「脳が不安だな」と感じることが増えたからこそ、散歩は私の土台になりました。
散歩がいいのは、運動だけじゃなく「外の刺激」が入ることです。
季節の空気、人の声、景色の変化。これが脳のスイッチになります。
そして一番大事なのは、途切れない設計です。
長く歩けない日があっていい。雨の日もある。体調が悪い日もある。
そういう日に「ゼロ」にしない工夫があると、散歩は習慣として残ります。
歩けない日の“つなぎ”例(これで合格)
- 雨の日:玄関まで行く/外を見て深呼吸
- 体調が悪い日:家の中を3分だけ歩く
- 気分が重い日:ベランダに出て光を浴びる
- 忙しい日:5分だけ外に出る(5分でもOK)
私は「5分でもOK」にしています。
続けるコツは、頑張ることより「戻れる形」を先に作ることです。
4. 睡眠が乱れる(夜更かし・昼夜逆転)
睡眠が乱れると、日中の集中力や意欲が落ちやすくなります。すると外出が減って、会話が減って、食事も雑になって…と生活全体が崩れやすい。
眠れないときに大事なのは「寝る時間」より「起きる時間」です。
起床時間を固定し、朝の光を浴びるだけでもリズムは戻りやすくなります。
寝る前のスマホを少し短くする、夕方以降の長い昼寝を避ける、温かい飲み物で落ち着く。
こうした小さな整え方が、結果的に脳の疲れも軽くしてくれます。
5. 食事が単調になる(栄養が偏る)
老後は「作るのが面倒」で食事が単調になりがちです。パンだけ、麺だけ、お菓子で済ませる日が増えると、体も脳も材料が足りなくなります。
完璧な食事にしなくて大丈夫。おすすめは「足す」だけです。
卵・納豆・豆腐などのたんぱく質を一つ足す、味噌汁に冷凍野菜を入れる。これだけでも変わります。
続く人は“頑張る”より“ラクにできる形”を作っています。栄養は気合いではなく、仕組みで整えるのがコツです。
6. 水分をとらない(脱水ぎみになる)
意外ですが、高齢になるほど水分不足は起こりやすいです。「トイレが近くなるから」と控える人も多い。
脱水ぎみになると、ぼんやり・だるさ・頭が回らない感じが出やすく、生活のやる気も落ちます。
対策は簡単で、「タイミングを決める」こと。
朝起きたら一杯、散歩の後に一杯、食事のたびに一杯。温かいお茶でもOKです。水分は“気が向いたら”だと忘れるので、“行動にくっつける”のが続きます。
7. 目や耳の不調を放置する(会話と外出が減る)
見えにくい、聞こえにくい。これを放置すると、会話が疲れて人を避けるようになり、外出も億劫になります。
つまり目や耳の不調は、孤立につながりやすいんです。
「年だから仕方ない」で止めずに、眼科・耳鼻科・補聴器相談などを一度検討するのは価値があります。
聞こえが改善すると会話が戻り、会話が戻ると外へ出る気持ちも戻りやすい。ここは生活の流れを変えるポイントになりやすいです。
8. 薬・通院・健診をやめる(持病管理が崩れる)
血圧、糖、脂質などの管理が崩れると、脳にも影響しやすいと言われます。
老後は「もういいか」と通院をやめたくなる瞬間が来ます。でもそのタイミングほど、相談して調整するのが安全です。
薬をやめたいなら、自己判断でやめずに「減らせるか」「別の方法はあるか」を医師に聞く。
健診も年1回でいいので続ける。持病管理は面倒に見えて、実は“脳を守る生活の土台”になります。
9. 新しいことを避ける(変化ゼロの生活になる)
脳は変化で刺激されます。だから「新しいことを避ける生活」が続くと、暮らしが単調になりがちです。
とはいえ、難しい挑戦は必要ありません。
いつもと違う道を歩く、新しいスーパーに行く、簡単な間違い探しを5分やる。これで十分です。
大事なのは「ちょっと違う」を入れること。変化は脳のスイッチです。小さな違いが、気持ちと生活の張りを守ってくれます。
10. ストレスを抱え込む(相談しない・休まない)
ストレスが続くと、睡眠が乱れ、食事が乱れ、外出が減りやすくなります。つまり生活の悪循環が始まる。
特に真面目な人ほど「迷惑をかけたくない」と抱え込みがちです。私も、脳梗塞のあと“できない自分”がつらくて、気持ちを閉じた時期がありました。
対策は、頑張ることではなく“抜くこと”です。
休む日を作る、誰かに一言話す、好きなことを5分だけやる。ストレスはゼロにできなくても、溜めっぱなしは避けられます。
11. 「面倒」が増えて身だしなみ・片付けが崩れる
前兆として気づきやすいのが、暮らしの「面倒」が増えることです。
郵便物が溜まる、部屋が散らかる、支払いを後回しにする、同じ物を何度も買う。こうしたズレが増えてきたら、生活が回りにくくなっているサインかもしれません。
対策は「まとめて片付ける」ではなく、1分で終わる作業を決めること。
たとえば“郵便物はここ”の箱を一つ作る、“支払いの日”を固定する。暮らしは仕組みで軽くできます。
12. 予定がなくなる(カレンダーが真っ白になる)
予定がないこと自体は悪いことではありません。
でも「予定なし+会話なし+外出なし」が続くと、生活の刺激が減り、気持ちも沈みやすくなります。
おすすめは、“小さな予定”を入れること。
週1回の買い物、週1回の電話、月1回の外食。これで十分です。
特別なイベントより、続く予定。散歩でも、通いの場でも、趣味でもいい。予定は“脳の生活リズム”を作ってくれます。
ここからが本題:認知症を遠ざける「毎日の整え方」(完璧じゃなくていい)
ここは“完璧”を目指さないことがコツです。
続く形が一番強いです。
1)散歩は最強の“土台”になる(しげの実感)
私は毎日、30分〜1時間歩いています。
速く歩けない日もあります。途中で休む日もあります。でも、続けています。
散歩がいい理由(むずかしい理屈抜き)
- 外に出ると気分が変わる
- 足を動かすと体が整う
- ついでに人に会う(会釈だけでも)
- 帰ってくると眠りやすい
散歩は「運動」だけじゃなく、孤立を防ぐ入口にもなります。
続けるコツ(30分できない日もOK)
- 10分×3回に分ける
- 家の周りを1周だけ
- 雨の日は家の中で足踏み
- “歩けた日”をカレンダーに丸(5分でもOK)
大事なのは、できない日を責めないこと。
続けるためには、責めない仕組みが必要です。
2)会話を増やす(“長話”じゃなくていい)
認知症が心配な人ほど、会話が減りがちです。
でも安心してください。会話は長くなくていいんです。
会話を増やすミニ習慣
- 朝:一言だけLINE(スタンプでもOK)
- 散歩中:近所の人に会釈
- 週1:誰かと電話5分
- 月1:外食 or 喫茶店
「うまく話せないから…」と思う日もあります。
私も失語症があるので、気持ちは分かります。だからこそ、短くてもいい/少なくてもいいで続けます。
3)睡眠は「寝る時間」より「起きる時間」
眠れない夜はあります。
そんな時に「早く寝なきゃ」と焦ると、余計眠れなくなる。おすすめはこれです。
睡眠を整えるコツ
- 起きる時間だけ固定
- 朝に光を浴びる
- 昼寝は短め(長い昼寝は夜に響く)
- 寝る前スマホを短く(できる範囲で)
4)食事は“足す”だけで脳が喜ぶ
完璧な栄養管理は疲れます。だから私は「足す」だけにしています。
“足すだけ”ルール
- たんぱく質を1つ足す(卵・納豆・豆腐・魚・鶏)
- 野菜を1つ足す(味噌汁に冷凍野菜でもOK)
- 水分をこまめに(温かいお茶でもOK)
5)脳トレは「難しい」より「続く」が勝ち
脳トレはやりすぎると疲れます。だから軽いのでOK。
続きやすい脳トレ例
- 数独(簡単なもの)
- 間違い探し
- 音読(短い文章)
- 日記を2行だけ
- その日の散歩で見たものを3つ書く
6)健康診断・血圧・糖は“脳を守る”ために見る
認知症の予防は、脳だけの話ではありません。
血管や代謝の状態を整えることが、遠回りに見えて近道になることがあります。
続けるコツ
- かかりつけ医を作る
- 診察で聞くことをメモ
- 「面倒だからやめる」をしない
7)目と耳のメンテは“外の世界を守る”
会話が聞き取りにくいと、人と会うのが疲れます。
見えにくいと、外出が億劫になります。
この“億劫”が積み重なると、孤立につながりやすい。
だから、目と耳のことは「年だから仕方ない」で終わらせない。
ここは本当に大事です。
早めに気づくためのチェック(しげ式:やさしい版)
ここ数か月で増えたものにチェックしてみてください。
生活のチェック
- 予定を忘れることが増えた
- 支払い・手続きが面倒で放置が増えた
- 探し物が増えた
- 同じ物をまた買ってしまう
会話のチェック
- 人と話すのが面倒になった
- 会話が続きにくい日が増えた
- 電話やLINEを避ける日が増えた
行動のチェック
- 外出が減った
- 散歩や買い物が億劫になった
- 趣味をやめた
- 新しいことが怖い
**3つ以上が「増えてきた」**なら、一度相談も選択肢です。
早めほど、できることが増えます。
1週間で整える「やさしい習慣プラン」(今日から使える)
全部やらなくてOK。できるところだけ。
月:散歩30分(短く分けてもOK)
- 10分×3回でも合格
火:誰かに一言だけ連絡
- LINEスタンプでも合格
水:食事に「たんぱく質」を足す
- 卵・納豆・豆腐、どれか1つ
木:睡眠のために「起きる時間」を決める
- 寝る時間はバラバラでもOK
金:脳トレ5分(簡単でOK)
- 間違い探しでもOK
土:買い物ついでに少し遠回り
- 外の刺激を足す日
日:休む日(ストレスを抜く)
- 休むのも習慣です
おわりに:不安は「小さな行動」に変えられる
認知症が怖いのは自然なことです。
でも怖さのまま固まると、外出や会話が減り、生活は小さくなってしまいます。
だから私は、散歩を続けています。
30分の日もあれば、1時間の日もある。雨の日は短く、体調が悪い日は家の中だけ。
それでも「ゼロにしない」ことが、明日の自分を助けてくれると感じています。
もしあなたも不安があるなら、まずは一つだけ。
散歩を5分でもいいから“続く形”にする。
それだけで、生活の土台は変わっていきます。